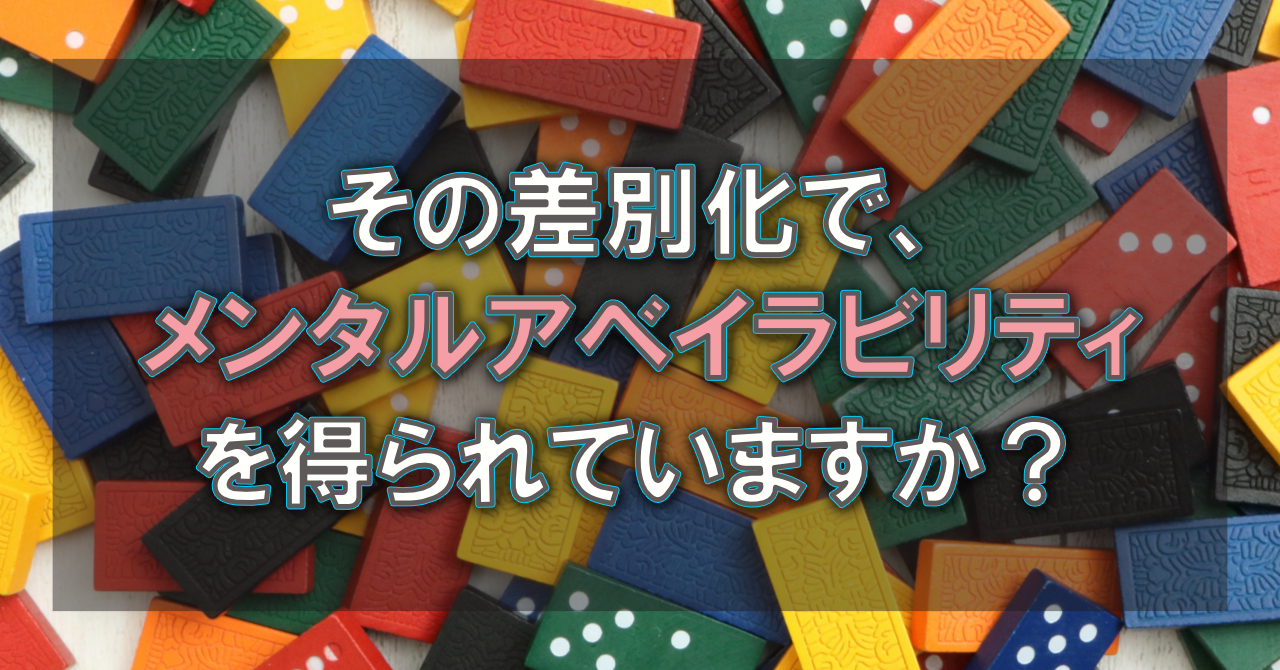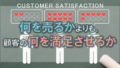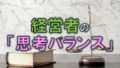ドラマに出てくる企業プレゼンのシーン。
「ライバル社との差別化をはかることで・・・」聞いたことありますよね。
リアルな世界では、とくに中小企業の戦略でありがちだと思います。
差別化って、わりと売り手の自己満足であることが多く、お客さんはほとんど気付いていないように思うのです。
大事なことは、必要な時に思い出してもらえるか。
このことを、メンタルアベイラビリティといいます。
ビジネスには長期目線と短期目線の両方が必要で、そのバランスも需要です。
これが、偏って語られることが多いので、インプットの少ない経営者は戦略も偏ってしまうことがあります。
とくに、スモールビジネスを経営しているひとはマスマーケティングが難しいことは実感しているでしょう。
ある程度ビジネスが回り始めると、囲ったお客さんを大切に、新規獲得は後回しになりがちです。僕はまさにそのタイプでした。
それが弱者の戦略だというくらいに思っていましたが、自分のマーケットを広げるということも、実は同じくらい大切だという気づきです。
この記事では、スモールビジネスでマスマーケティングを考えるさいにやってしまいがちな、「差別化」の落とし穴と、マスマーケティングによるメンタルアベイラビリティの重要性について話をしましょう。
長期的なブランディングと短期的なマーケティング
最近は、経営論のなかにも「ブランディング」という言葉をよく聞くようになりました。
一般の方が「ブランド」という言葉を使うときには、高級品のことを指すことが多いですね。特に女性向けのアパレルがイメージしやすいでしょう。エルメス、ルイヴィトン、プラダみたいなメーカーです。
マーケティング用語におけるブランディングというのは、文字通り自社のブランドを確立していくことではありますが、必ずしも高級感を出しましょうという意味ではありません。
例えばコカ・コーラは、1本100円程度で買えるわけですが、世界的なブランド力がありますね。私たちが暑い夏に「喉が渇いた!」って思ったら、コカ・コーラが選択肢に入る人は少なくないでしょう。
「いやいや、私はそんなにコーラ好きじゃなくて、飲んでもせいぜい年に1回くらいかな」って思うかもしれません。
ところが、コカ・コーラの売上の約半分は、そんなあなたのような年に1回くらいしか飲まない人です。
まさに、ブランディングに成功している例ですね。
ブランディングについて掘り下げるとここでは語りきれないので別な機会にします。
コカ・コーラの場合は、それが地球レベルで成功しているのでイメージしにくいかもしれませんが、方向性としては、たとえ一人で始めたスモールビジネスであっても、そこに近づける方が有利に働く可能性があります。
長期的なブランディングを成功させた要因は何かと考えれば、長年やり続けてきた短期的なマーケティングの積み重ねに他なりません。
思えば僕らは子どもの頃から、コカ・コーラのことはよく知っています。たぶん、世界中の多くの国でそうでしょう。
一度でも営業職の経験がある人ならわかると思いますが、ビジネスにおいて新規獲得というのは大変なことです。
しかし、ルート営業のみに甘んじることなく新規に目を向ける努力を忘れてはいけません。
ここで、スモールビジネスに特化して考えると、新規獲得向けのマーケティングということはつねに意識する必要があります。
「差別化」の致命的な欠点
新規獲得には、二種類あります。
ひとつは、まだどこのファンでもない潜在的な顧客を掘り当てる方法です。
あなたの商品ジャンルに、なにかのきっかけでこれから興味をもつかもしれません。
もうひとつは、ライバル会社から顧客を奪う方法。
これは、実はペプシ・コーラが上手なことでも知られています。コーラなんて飲まない人を口説くよりも、コカ・コーラを飲んでいるにアプローチした方が効率よくマーケティングできるのです。
そこだけ書くと卑怯な方法にも思えてしまいますが、ほとんどの業界で、最大手以外は、たいてい後者のタイプでマーケティングしています。
実際にやるとわかりますが、欲しがってもいない顧客に、まずはその必要性から伝えなければならないというのは、とても効率が悪いです。
コーラを飲む習慣が無い人にペプシの良さを語るより、コカ・コーラをよく飲む人に「今回はペプシにしてみませんか?」と勧める方が、はるかに売りやすいのは想像が付きますね。
そこで、僕らが考えるのは「差別化」なんです。
差別化、とても大事です。
同じだったら、あなたの商品を買う理由がない。
でも、僕自身が長年商売をやってきて感じるのは、差別化って、目先の売上にはほとんど影響しないのです。
もちろん、商品スペックを詳細まで比較して、欲しい機能があるとか、優れている点があると比較して購入する場合もあります。
思い出してみてください。
あなた自身が買い物する際に、全ての商品やサービスに対して、そんな検討をしているでしょうか。
カワイイから気に入った、美味しいそう、こっちの方が安い、担当の人が感じ良かったからお願いした・・わりとそんな感じじゃないですか。

差別化が、意味があるのはもっと先の話で、買った後に他社製品と冷静に比較されたときに、「やっぱりこの商品を選んで良かった」と思われるためには有効です。だから、差別化という視線も忘れてはいけません。
ただ、差別化することで、選んでもらえると考えるのは、売り手のやりがちな勘違いです。
差別化の致命的な欠点は、顧客は、そんな違いに気付いていないことが多いということです。
熱狂的ファンよりもそれほど興味が無い人への メンタルアベイラビリティ
勉強家のあなたならパレートの法則の話しを聞いたことがあるかもしれません。
8:2の法則で、例としても様々なバリエーションがあります。
マーケティングに近い話しでパレートの法則を挙げると、「2割のお客さんが売上の8割を生む」ということです。
肌感覚的にはけっこう当たってるような気もしますが、冷静にグラフにしてみると、意外とそうでもないことも多いようです。
先ほどから例に挙げているコカ・コーラも年に1回飲む程度のライトユーザーの売上が半分を占めているということでもわかります。
昔は、全てがローカルビジネスですので、どんな商売でも常連がつきやすかったのです。
だから、囲ったお客さんだけ相手にしていれば成り立ったということがあるのでしょうけど、ネットが普及した現代はそうはいきません。
情報過多の顧客の興味は簡単に余所に流れてしまいます。
マスマーケティングは時代後れだと一時期は言われましたが、最近はまた見直されています。
やはり、多くの人に自社商品の魅力を知ってもらうことは、売上持続のためにとても重要です。
先述したように、まったく興味が無い人に勧めるのは難しいことです。
だからといって常連ばかり囲っていてもだめ。では、どのような層を狙うのかといえば、「それほど興味がない人たち」です。
具体的に何をめざすかということ、「メンタルアベイラビリティ」ということです。
これは、あなたの扱うサービスが必要だと思ったときに、思い出してもらえるか、ということです。
似ている言葉で、「フィジカルアベイラビリティ」というのもありますが、こちらは必要な時に実際にすぐに手に入るかということです。コンビニやチェーン店が多店舗展開するというのはそういうことですね。
コンビニといえば?「セブンイレブンかな・・」っていうひとは、メンタルアベイラビリティで決めていますし、買い物したいときに近くにあったのがローソンだったので入ったという人は、フィジカルアベイラビリティによって、決めたことになります。
コンビニの例でもわかるとおり、スモールビジネスで、フィジカルアベイラビリティに重きを置くのは難しいです。
つまり、私たちは目指すべきは、メンタルアベイラビリティ。ターゲット層の人が「○○といえば?」と考えたときに、自分のことを思い出してくれるか?ですね。
思いつきさえすればオンラインショップですぐに注文できるというのは、フィジカルアベイラビリティのひとつですので、切り離されるものではありません。
人脈というと、自分にとって有益な人のことを指すように思われがちですが、そういう意味では人脈は多いに越したことはありません。
ある問題が発生した場合、「それなら知り合いにやってる人がいるよ」と言ってもらえる力は、非常に大きいです。
それは、リアルでもネット上でも同じことです。
どれだけ多くの人と接触を増やしたり、独自性で目立てることを考えて、必要な時に思い出してもらえるか。
そのようなマスマーケティングを考えて行きましょう。
まとめ
絶大なブランド力も、短期的なマーケティングの積み重ねです。
ネットの普及でライトユーザーがおおくなる現代は、改めて新規獲得に向けたマスマーケティングは重要です。
その際に、差別化は大事ですが、意外にも顧客はその違いに気付いていません。
マーケティングの際に目指すのは、メンタルアベイラビリティ。
必要な時に自分のサービスを思い出してもらえるか。
スモールビジネスだからこそ、そのようなマスマーケティングを考えましょう。
この記事を書いた人
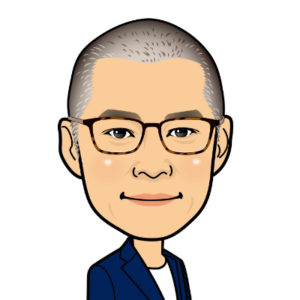
長岡慶一郎。札幌出身。システム開発、寺院仏具の仕事などを経験。合同会社長岡念珠店を経営。販売だけでなく、数珠の作り方や知識に関するオンラインスクールの運営中。現在は、経営ノウハウを生かし、スモールビジネス向けのコンテンツを発信、起業・副業したい人のための個人向けコーチングにも注力している。2022年より「まなびライフオンライン講座」もサービス開始。
お問合せはこちら